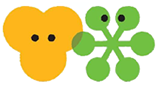いつまでも湿地ではいられない。
2018年12月06日(木)
みなさんは植生遷移ということばを聞いたことがありますか。簡単に言うと裸地から草原、低木林、高木林へと長い年月をかけて植生が変化していく過程を言います。同じように水辺では湖沼から湿地、低木林、高木林へと変化していきます。
東山植物園は文字通り、他から植物を持ってきて展示するところなので、一見植生遷移とは無縁のように思えますが、それでもやはり全く人の手をいれずに放置すれば、いずれはタブノキやスダジイなどの高木林(陰樹)に遷移していくでしょう
 【人の手がはいらなければ、いずれはこの景色は見られなくなる。】
【人の手がはいらなければ、いずれはこの景色は見られなくなる。】
また湿地園においても同様です。湿地の植物は貧栄養で育つ植物ばかりです。秋から冬に枯れる草をそのまま放置すればそれが腐り、富栄養化していきます。またそれらが堆積することで陸地になり低木林(ヤナギ類)、高木林(ハンノキ、ミズキなど)へと遷移していきます。
つまりみなさんが見ている湿地は、植生遷移の中の一コマと言えます。東山植物園の湿地園では植物管理人たちが富栄養化にならないように毎年秋から冬にかけて枯草を刈り、湿地の外に持ち出しています。手間の掛かる作業ですが、おかげで毎年シラタマホシクサ、サワギキョウ、ミソハギ、サギソウなどを見ることができます。
【一面にシラタマホシクサが生えていました。】
【富栄養化しないように刈り取って持ち出します。】
【人の手をいれなければ、やがて湿地は消滅します。】
昔は今のように公共土木施設が整備されていなかったため、植生遷移によりもとの湿地が消滅しても、山崩れや川の氾濫による地形の変化により新たに湿地ができていました。しかし今は技術が進歩したことで、そうしたことが起こりにくくなってきたため、今ある湿地を守っていかなければ、いずれはなくなってしまいます。
名古屋市内では守山区に八竜湿地があります。実はこちらの湿地も人の手が入ることで良好に維持されています。1995年から自主メンバーによる保全活動を開始し、2006年からは条例に基づく緑のパートナーとなり『水源の森と八竜湿地を守る会』のみなさま活動により維持されています。
八竜湿地では、毎年春にはハルリンドウが咲き、秋にはシラタマホシクサが咲きます。そのほかにもここでは多くの湿地植物を見ることができます。このようにずっと保全をしてきてくださった方の努力がなければ、今頃八竜湿地もなくなっていたかもしれません。
植物園での役割のひとつに種の保存があります。本当はあるべきところに保全されるのが望ましいのですが、次々と開発が進む中、今後植物園の果たす役割も大きくなっていきます。
○お知らせ○
植物園では見ごろの植物の情報を花マップで提供しています。
ご来園の際はぜひご利用ください。
植物園緑地造園係長 太田 幹夫